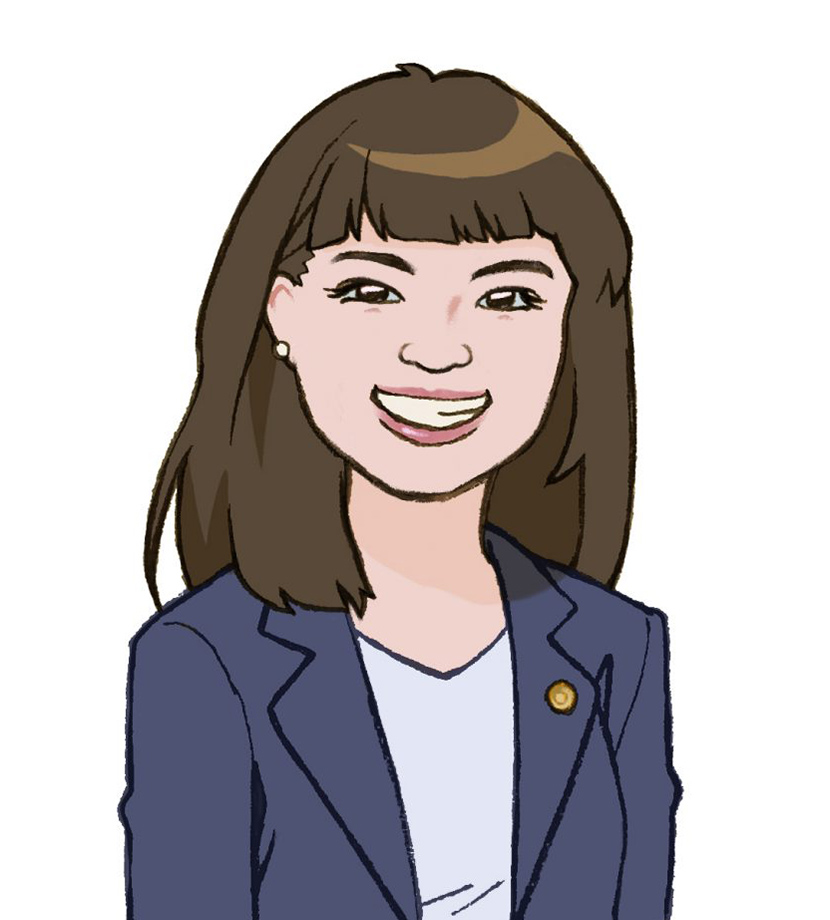病院・クリニック・医療機関のための 法律相談
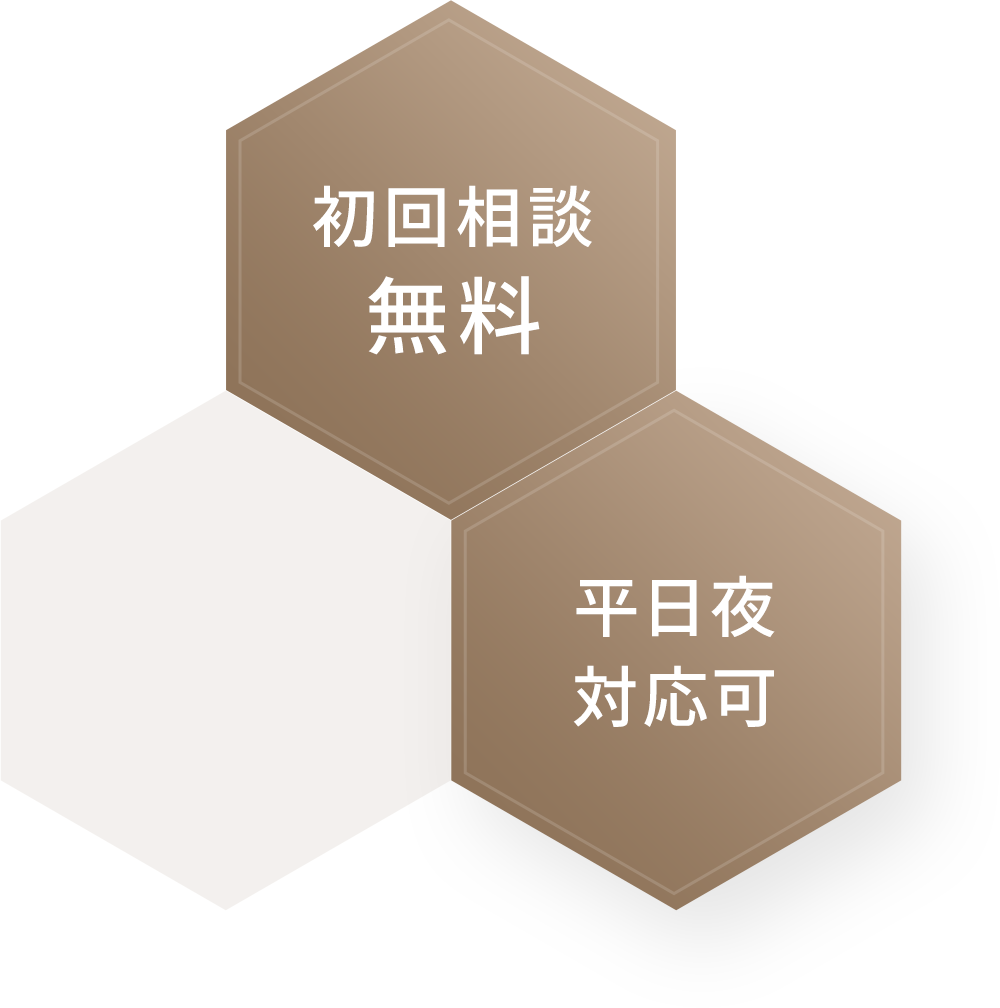
BUSINESS取扱業務のご案内
様々な法律問題について、
包括的な法務サービスを提供します。
医療法務に精通している私たちに
お任せください。
REASON瀬合パートナーズが
選ばれる理由
-
 医療機関特有の法律問題について
医療機関特有の法律問題について
詳しい弁護士が対応医療機関特有の法律問題に詳しく、数多くの法律問題を解決した実績と経験を有しています。
それぞれの医療機関にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 -
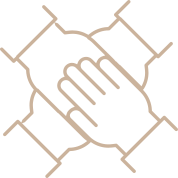 複数名体制で、
複数名体制で、
⼿厚いサポートを実現当事務所には10数名の弁護士が在籍しており、神戸・姫路の拠点間も密に連携しています。
ご相談やご依頼には基本的には複数名の弁護士で対応し、手厚いサポートをさせていただきます。 -
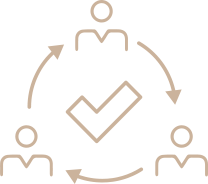 Webやメールでの
Webやメールでの
ご相談にも
迅速に対応忙しくて時間がない場合でも、Web面談やメール、チャットワーク、お電話などでの相談により迅速に対応させていただきます。緊急時の相談にも優先してご対応させていただきます(いずれも顧問契約をしていただいたお客様のみ)。
ATTORNEYS弁護士紹介

代表弁護士
瀬合 孝一
kouichi segou
医療機関を法的リスクから守る
法律事務所瀬合パートナーズ 代表弁護⼠の瀬合孝⼀です。
当事務所は神戸と姫路の2拠点に事務所を構え、地域の皆様に質の高いリーガルサービスを提供することを目指しております。
医療関係の皆様には、多忙な日常業務の中で、トラブルに対応する時間的・精神的余裕がないことが多いと思います。そのようなとき当事務所がサポートさせていただくことで、医療関係の皆様のご負担を減らし、業務に専念できる環境づくりをお手伝いさせていただければと思います。
代表弁護士
瀬合 孝一
kouichi segou
COLUMN医療法務に関する
弁護士コラム
様々な情報を掲載しております。
ぜひお役立てください。
-
医療法人の経営権争いが起きたときの対応について弁護士が解説
1.医療法人における「経営権争い」とは? 医療法人には、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。社員総会は、株式会社の株主総会に相当しますが、株主総会とは異なり社員が一人一個の議決権を持ち、同権利を行使します。そのため、株式会社のようにより多くの出資を行ったから、多くの議決権を有するということにはなりません。より多くの社員の賛同を得ることができれば、多数派になるという形になります。 そして、「経営権争い」とは、法人の意思決定権や運営の実権を巡って、理事や出資者、あるいは親族間で対立が起こることを指します。上記のような、医療法人の仕組みの下では、より多くの社員の賛同を得られれば、多数派となり、法人の意思決定権や運営の実権を握ることにつながります。したがって、争いが顕在化すると、これまで医療法人での貢献度が高かった人物ですら、多数派により法人から追い出されることもあり得ます。 2.経営権争いが表面化したときの典型トラブル 経営争いが表面化した場合、以下のようなトラブルが発生することが典型的には見られます。 ⑴ 理事会の開催や決議をめぐる紛争 理事の任免や報酬、重要な契約の締結などを巡って理事会の決議がまとまらず、法人運営が停滞す る事態です。無効な決議や、逆に決議ができない状況が続くと、法人の法的な正当性が問われる可能性もあります。 ⑵ 理事長の解任・交代に関する争い 理事長の解任や交代を巡って、現職理事長と他の理事や出資者が対立するケースがあります。理事長の権限が大きいため、このポジションを巡る争いは特に深刻化しやすいです。 3.弁護士が関与するメリット ⑴ 法的立場の整理と主張の明確化 関係者間で法的な権利義務が不明確なまま対立が続くと、感情的な争いになりやすいです。弁護士が介入することで、法や、定款、規則といった正当な根拠に基づき、法的に有効な主張を構築することが可能になります。 ⑵ 訴訟対応による 最終的に訴訟に発展した場合でも、弁護士が最初から関与していれば、訴訟対応がスムーズに進みます。法人の混乱を最小限に抑えることが期待できます。 4.トラブルを未然に防ぐためにできること ⑴ 定款・規則の見直し 医療法人の定款や規則が曖昧な場合、解釈を巡って争いが生じやすくなります。専門家の助言を得ながら、意思決定のルール、理事長の選出方法、任期、解任手続きなどを明文化しておくことが重要です。 ⑵ 定期的に弁護士などの専門家によるチェックを受けることで、法人内部のリスクを早期に発見し、適切に対処することができます。特に親族経営の場合、身内の間で問題が見過ごされやすいため、外部の視点は非常に重要です。 5 まとめ 医療法人内部において、経営争いが生じますと、法人の存続が危ぶまれるほどの重大な事態に陥りかねません。 そこで、トラブルが生じる前、あるいはトラブルが生じた後にでも、弁護士に相談し混乱を最小限に抑えることが極めて重要となって参ります。
-
医療過誤が発生した病院が最初に取るべき対応と法的責任の整理
1.病院で医療過誤が起きてしまったら 医療の現場では、どれほど注意を払っていても、予期せぬミスや判断ミスにより、患者に何らかの被害が発生してしまう場合があります。医療行為は人の手によって行われるため、このような事故を完全に防ぐことは難しいですが、病院側に過失があった場合には、法的責任を問われる可能性もあります。 そのため、医療過誤が発生した場合には、病院には、迅速かつ適切な対応が求められます。本記事では、医療過誤が発生した際に病院が行うべき初動対応と、病院側に生じる可能性のある法的責任について解説します。 2.医療過誤とは? 医療過誤とは、医療行為に際して発生した予期せぬ結果(医療事故)のうち、医療従事者が医療の遂行において医療的準則に反したことが原因であるものをいいます。例えば、手術部位の取り違えや投薬ミスなどがこれに該当します。 3.医療過誤が発覚したときに、病院側が最初にとるべき対応 医療過誤が発生した場合には、まず、患者の状態を把握し、必要な応急処置を迅速に行うことが最優先です。次に、医療過誤が生じた患者やその家族に対し、医療過誤の内容について誠意ある説明を行うことが重要です。 そして、関係書類やデータの調査、関係者に対するヒアリングを行い、事実関係を正確に把握することで、医療過誤が生じた原因を究明することが求められます。調査に際しては、例えば、第三者委員会を設置する等、透明性を確保することが望ましいです。 その後、医療過誤の原因に関する調査結果を踏まえ、患者に対して行う損害等賠償、医療過誤の再発防止策について検討することになります。 4.病院が負う法的責任とは 医療過誤によって患者に損害が生じた場合には、病院や医師は以下のような法的責任を問われる可能性があります。 まず、病院や医師は、患者やその家族から、医療過誤によって患者やその家族に生じた損害の賠償を求められる可能性があります(民事責任)。 次に、医療過誤によって患者に傷害を負わせ、又は、死亡させてしまった場合、医療過誤を生じさせた医師に、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります(刑法211条、刑事責任)。業務上過失致死傷罪が成立する場合には、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処せられます。 更に、医師や看護師は、国から与えられた免許に基づいて業務を行っていますので、医療過誤を発生させた医師や看護師には、厚生労働大臣によって、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消し等の行政処分がなされる場合があります(行政責任)。 5.病院内で注意すべき対応ポイント 病院が、医療過誤が発生した場合の対応において注意すべき点としては、まず、医療過誤により患者の生命に危機的状況が生じた場合には、患者が強い不安におそわれる可能性がありますので、患者に対する心理的な配慮が必要である点が挙げられます。 また、患者の家族に対する連絡及び説明は速やかに行うことも重要です。家族に対しては、容態が急変した事実を告げた上、現在判明している事実関係の説明、応急処置の内容や今後の治療方針に関する説明を行う必要がありますが、トラブル防止や信頼関係の維持のために、説明時点で未だ明確になっていないことを推測で述べる等、不正確な説明を行うことのないように注意する必要があります。 また、患者への損害賠償の要否やその内容、再発防止策の検討のために、医療過誤発生時の状況及び経過については、正確かつ客観的な記録を残しておくこと、各種証拠を保全することも必要です。 6.弁護士の役割と相談すべきタイミング このように、医療過誤が発生した場合、病院には、患者の被害に対する応急処置以外にも、迅速かつ適切な対応が求められます。特に、初動対応においては、注意すべき点も多く、病院側にとって、緊張を強いられるものでしょう。 医療過誤が発生した場合に、弁護士に速やかにご相談頂けましたら、患者やその家族に対する対応の内容、方法についての具体的な助言や、保全すべき証拠の内容や保全の方法についての具体的な助言を受けることができます。また、患者やその家族との間の信頼関係の維持が困難であると考えられる場合には、弁護士が病院側の代理人となって、患者やその家族との間の示談交渉や訴訟への対応を行うことができます。その他、医療機関の内部ルール整備や、コンプライアンス体制の見直しにも、弁護士が関与することができます。 このように、医療過誤が発生した場合には、速やかに弁護士に相談し、法的な観点からの助言等を受けることによって、迅速かつ適切な対応により被害の拡大を防ぎ、法的リスクを最小限にとどめることが重要です。 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズでは、病院やクリニックを経営する医師の皆さまから、様々なご相談をお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
-
医療過誤を未然に防ぐための弁護士の必要性
1 医療過誤でお悩みの方へ 医療の現場では、高度な専門知識と緻密な作業が求められるため、十分に注意を払っていたとしても、医療機器の不良、過重労働などの影響で、医療過誤が発生してしまうことがあります。 実際に医療過誤が発生した場合、患者やその家族だけでなく、医療機関にも大きな損害が生じます。本記事では、医療過誤の原因と影響、医療過誤を未然に防ぐための対策について解説します。 2 医療過誤が起きた際の損失 医療過誤が発生した場合、医療機関は、患者側の以下の損害について、支払いを求められる可能性があります。・財産的損害(治療費、看護費、介護費、休業損害、逸失利益等)・精神的損害(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等) その他にも、医療機関の信用の失墜・社会的非難を招き、医師や看護師の士気低下、離職を誘発することにもなりかねません。 以上のとおり、医療過誤は一度発生してしまうと、その損失は多岐にわたります。そのため、事後的な対応だけでなく、事前に予防することが極めて重要です。 3 医療過誤が起きた際の対応 実際に医療過誤が起きた場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。主な対応としては、以下のものが挙げられます。 (1) 患者や遺族への説明と謝罪 医療機関には、診療契約上の説明義務(民法656条、645条参照)があるため、患者や遺族から説明を求められた場合には、回答する必要があります。 説明にあたっては、関係者へのヒアリング、カルテその他の医療記録を総覧することで事実関係を精査し、調査結果をまとめたうえで、できる限り速やかに、患者やその遺族に説明することが求められます。 十分に事実関係が調査できていない場合、注意義務の前提となる予測可能性を認める発言など、医療機関にとって不利な発言をしてしまい、録音を残されてしまう可能性があるため、注意が必要です。 また、患者やその遺族に対する謝罪は、過程ではなく結果に対する謝罪にとどめ、謝罪に至るまでの経緯、謝罪時の具体的な状況については、カルテや看護記録に記載しておくことが望ましいです。 (2) 保険会社への事故報告 医療賠償責任保険を適用する前提として、保険会社への事故報告書の提出が必要になります。同報告書を提出しないまま、患者や遺族との和解を成立させてしまうと、保険会社との間で法的責任や解決方針について見解の相違が生じた場合、保険金の全部又は一部が支払われない可能性がありますので、ご注意ください。 4 医療過誤が起こる要因 医療過誤は、主に以下の3つの要因が重なり合って発生します。そのため、いずれの要因についても、法的・制度的是正を行うことが重要です。 (1) 人的要因 ・疲労や注意力の低下・知識・技術不足・スタッフ間のコミュニケーション不足 (2) 機械的要因 ・医療機器の老朽化や故障・定期点検・整備の不徹底・操作マニュアルの未整備 (3) 環境的要因 ・過重労働による集中力の低下・シフト体制の不備・劣悪な労働環境や人員不足 5 医療過誤を未然に防ぐために弁護士が対応できること (1) 保守・メンテナンス契約の最適化 医療機関では、様々な高度医療機器が使用されますが、これらの安全性を維持するには、保守・メンテナンス契約が不可欠です。もっとも、保守・メンテナンス契約は、外部の専門業者と締結されることが多いため、十分に内容を精査しなかった結果、責任の所在が不明確であり、後にトラブルが生じてしまうケースがあります。 そのため、弁護士が、医療機器保守契約のリーガルチェックを行い、定期メンテナンスの義務化や、不具合発生時の責任範囲の明確化、損害が発生した場合の補償条項などを整備することで、機械的要因による過誤のリスクを軽減することができます。 (2) 長時間労働・過重労働対策 近年、医療現場における長時間労働・過重労働の問題が深刻化しています。特に医師・看護師を中心とした現場では、24時間体制の勤務や人員不足による業務負担が常態化し、健康被害や医療ミスのリスクも高まっています。 2024年4月からは、医師にも「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制(年960時間等)が適用され、法令遵守と労務管理の見直しが強く求められるようになりました。 こうした状況のなかで、弁護士が、勤務体制の適正化や三六協定の見直しなど、労働時間管理、過重労働対策のアドバイスを行い、職員の疲労軽減や働きやすい環境づくりをすることで、人的要因によるミスを防止することができます。 (3) 勤務環境・安全衛生規定 医療現場には、感染症、医療廃棄物、放射線、化学物質、夜勤・長時間勤務など、多様なリスクが存在するため、このような医療現場特有のリスクに対応した医療従事者の健康・安全を守るためのルールを整備することが欠かせません。 そのため、弁護士が、最新の労働安全衛生法に基づき、労働災害の予防、衛生管理、緊急時対応等を定めた、安全衛生規程を作成・運用することで、環境的要因による医療過誤を防ぐことができます。 6 弁護士の必要性 以上のとおり、医療過誤は、人的要因だけでなく、機械的要因、環境的要因が重なり合って生じます。 そのため、医療過誤を未然に防ぐためには、長時間労働の是正、医療機器保守契約のリーガルチェック、安全衛生規程の新規作成・改訂が必須となります。 現在の医療機器保守契約を見直したい方、労働時間の管理体制に不安がある方、今後の法改正に備えたい方は、是非弁護士にご相談ください。
-
医薬品・医療機器の安全管理体制の確保の必要性について
1 はじめに 医薬品や医療機器は、患者の健康や命に直結する極めて重要な製品です。その使用・管理には厳格な基準と体制が求められており、万が一不適切な取り扱いがあれば、深刻な健康被害や医療事故を引き起こしかねません。こうした背景のもと、医薬品・医療機器を取り扱う企業や医療機関には、安全管理体制の確立が強く求められています。本稿では、薬機法などの関連法令に基づいた安全管理体制の必要性と、具体的な対応方法について解説します。 2 安全管理体制確保の重要性 医薬品や医療機器は、医療現場で日常的に使用されるものである一方、取り扱いを誤れば、重大な事故や健康被害の原因となるリスクも抱えています。例えば、保管方法の不備により薬剤が変質してしまったり、医療機器の点検不足が原因で正確な診断や治療ができなかった場合、患者の安全を著しく損なう恐れがあります。 そのため、企業や医療機関は、単なる販売・使用にとどまらず、「安全に使用できる状態を維持する」ための体制づくりが求められており、これは企業の社会的責任の一部でもあります。 3 薬機法における安全管理義務 薬機法では、製造販売業者に対して、厚生労働省令で定める基準に適合した品質管理及び安全管理を行うよう定めています。安全管理体制の構築・運用を義務付けている厚生労働省令は、以下のとおりです。• GVP(Good Vigilance Practice):製造販売後の安全管理を定めた基準。副作用や不具合、外国での安全性情報の収集・評価・報告、必要な措置の実施等を定めています。• GQP(Good Quality Practice):製品製造後の品質管理について定めた基準。品質管理責任者の設置、品質管理情報の収集・評価・報告等を定めています。 例えば、医療機器で故障や重大な不具合が発生した場合、厚生労働省へ一定期間内に報告する義務があり、状況によっては製品回収や注意喚起などの措置も求められます。これらの義務は、企業の任意の対応ではなく、法的な義務となります。 4 医療法や他法令との関連性 医療機関においては、薬機法のみならず医療法や労働安全衛生法、個人情報保護法などの法令も関係してきます。たとえば、医療法に基づく医療安全管理体制として、医療事故防止のための研修や報告制度の整備が求められており、医療機器の安全な使用・保守点検の体制もここに含まれます。 これらの法令は相互に関係しており、どれか一つを遵守すればよいというものではありません。すべての関連法令を俯瞰的に理解したうえで、横断的に整合性のある管理体制を構築することが求められます。 5 安全管理体制が未整備である場合のリスク 安全管理体制が不十分であることにより、以下のような深刻なリスクが発生します。 ① 行政処分・罰則のリスク 薬機法違反が認定された場合、営業許可の取消し、業務停止命令、罰金刑などの厳しい処分を受ける可能性があります。② 患者の安全を脅かすリスク 不具合製品の見落としや保守不良によって医療事故が発生した場合、患者の生命に直結する損害が生じ、訴訟リスクや社会的批判の的となります。③ 企業の信頼性・ブランド毀損リスク 一度でも事故や法令違反が公表されれば、社会的信頼の低下は免れず、企業価値や収益にも大きな影響を与えます。 6 薬機法に詳しい弁護士が介入するメリット 薬機法や関連法令に詳しい弁護士が関与することで、以下のような実効性ある支援が可能になります。 ① 内部規定やマニュアルの整備 医療機器安全管理マニュアルをはじめ、GVP手順書、緊急時対応マニュアルなどを法的視点から整備・更新。現場運用との整合を図ります。② 契約内容の適正化 保守・点検契約や販売契約において、「定期点検頻度」「部品交換基準」「故障時の代替機提供期限」などの条件を薬機法上の義務と一致させることで、後の紛争防止にもつながります。③ コンプライアンス研修の実施支援 従業員向けの法令順守研修や安全教育において、具体的事例や法的背景を交えた実践的な内容を提供することができます。 7 安全管理体制構築のための実務ステップ 安全管理体制を構築・運用するには、以下のステップが有効です。 ① 現状把握とリスクアセスメント 体制の抜け漏れやリスク要因を洗い出し、優先順位をつけて対応。② 内部体制と文書整備 責任者の任命、報告ラインの明確化、教育訓練計画の策定。③ 契約書・業務フローの見直し 安全性確保に直結する契約条件や業務手順を精査・改訂。④ 職員教育の実施と定着 継続的な教育とマニュアル周知により、実効性を高める。⑤ モニタリングと改善 定期的な監査・評価を通じて、体制の改善サイクルを構築。 8 まとめ 医薬品・医療機器の安全管理体制の構築は、企業や医療機関にとって単なる「義務」ではなく、患者の命を守るという「使命」です。法令順守と社会的信頼の確保を両立させるためにも、専門家の助言を受けながら、組織としての対応力を高めることが不可欠です。
-
医療広告ガイドラインとは?広告表示の際に注意すべき点を弁護士が解説
第1 医療広告ガイドラインとは? 医療広告については、医療法をはじめとした法律により制限されてきましたが、美容医療サービスに関する消費者トラブルの増加を受け、平成30年に医療法が法改正されたことでウェブサイトが規制対象となる等、規制の対象が拡大しています。医療広告ガイドラインは、医療広告に対する法的規制を前提として、医療機関が広告を行う際に遵守すべき基準を定めた指針となります。 第2 医療広告ガイドラインが適用されるもの・適用されないもの 1 医療広告ガイドラインが適用されるもの 医療広告とは、①患者を誘引する意図があること(誘因性)、②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能性であること(特定性)の2要件を満たすものと定義されます。この2要件に該当する広告は、医療広告として規制対象となります。 2 医療広告ガイドラインが適用されないもの 以下のようなものは、上記2要件を満たさず、原則、医療広告に当たりません。①学術論文、新聞記事②新聞や雑誌等での記事③患者等が自ら掲載する体験談、手記等④院内掲示、院内で配布するパンフレット等⑤医療機関の職員募集に関する広告 3 認められている広告内容 医療法第6条の5第3項には、以下の内容が広告可能事項とされており、その他の事項については広告することは出来ません。① 医師または歯科医師である旨② 診療科名③ 病院又は診療所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名④ 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無⑤ 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨⑥ 厚生労働大臣による認定を受けた医師(医師少数区域経験認定医師)である場合には、その旨⑦ 地域医療連携推進法人の参加病院等である場合には、その旨⑧ 入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項⑨ 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの⑩ 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項⑪ 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項⑫ 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項⑬ 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)⑭ 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもその他厚生労働大臣が定める事項⑮ その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 広告可能なのは、原則、上記各事項に限られるものの、以下のいずれの要件も満たした場合は、他の事項も広告することが可能です。① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること 第3 医療広告ガイドラインに抵触する広告の具体例 (1)広告が許可されていない事項の掲載 前記のとおり、医療法第6条の5第3項には広告可能事項が定められており、それ以外の事項については原則として広告することが出来ません。 (2)虚偽の広告 虚偽内容の広告は禁止です。「絶対安全な手術です!」 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」といった広告も、医学上あり得ないため、虚偽広告として禁止されます。 (3)他の病院や診療所と比較して優れているとする広告 自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することは禁止されます。例えば、 「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」 「当院は県内一の医師数を誇ります。」といった広告がこれに当たります。 (4)誇張表現を含む広告 事実を不当に誇張したり、人に誤認させる広告は禁止されます。「医師数○名(○年○月現在)」 といった広告も、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として取り扱われるので、実態に即した人数に随時更新する必要があります。 (5)患者の体験談を使用した広告 体験談については、個々の患者の状態等により感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあるため禁止されています。 (6)ビフォーアフターの写真を用いた広告 個々の患者の状態等により治療等の結果は異なりますので、誤認させるおそれがあるビフォーアフター写真等は禁止されています。もっとも、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合には、医療広告として認められます。 第4 広告の合法性を確認する手順 医療広告として禁止されるか否かは、以下の順で確認するのがよいでしょう。① 医療広告に該当するかどうかの確認 広告が医療広告の規制対象となる「誘引性」と「特定性」を備えているかを検討します。② 広告可能事項にあたるかの確認 医療広告にあたる場合、広告の内容が医療法第6条の5第3項の広告可能事項の範囲内であるかを確認します。③ 医療広告で禁止された内容かを確認 誇大表現や虚偽記載がないかをガイドラインに基づいて確認します。 第5 規定違反が発覚した場合の対応措置 違反が疑われる場合、医師や病院に対し、説明を求める等の任意調査、報告命令又は立入検査が行われることになります。そして、違反が確認できた場合、行政指導により広告の中止や内容の是正を求めることになります。行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事例の場合には、違反広告を行った者に対し、広告の中止命令又は是正命令が行われます。 虚偽広告であった場合や中止命令若しくは是正命令に従わなかった場合には6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、報告命令又は立入検査に対する違反の場合には20万円以下の罰金が科されます。 違反の疑いがあるとして調査が開始された場合には、広告内容について積極的に説明を行う必要がありますが、任意での広告中止又は内容の是正を求められた場合には、指導に応じた方がよいでしょう。 第6 弁護士の必要性 広告内容の適法性確認や行政指導への対応には、法的知識が求められます。作成した広告が医療広告ガイドラインに違反する場合、刑事罰を科される可能性もあるため、事前に専門家に相談することが重要です。医療機関としての信頼を守るためにも、新たな医療広告を出す際は、事前に弁護士にご相談ください。
-
人材紹介のトラブルと金銭問題:医療機関経営者が知っておくべき注意点
1 医療機関における人材紹介のトラブルの現状 医療機関が人材紹介サービスを利用する際には、効率的な採用が期待できる一方で、トラブルや金銭的問題が発生するリスクもあります。実際に、人材紹介サービスを利用する医療機関からは、以下のようなトラブルが報告されています。・人材紹介会社との契約内容が不明瞭で、返金や保証が適切に行われない。・高額な紹介手数料を支払ったにも関わらず、紹介された人材が短期間で退職する。・信頼性の低い業者の選定により、予想外の損失が発生する。 2 人材紹介サービスで起こりうる金銭トラブルとは? 以下のような場合に、人材紹介会社との間で金銭的トラブルが発生するおそれがあります。・不明確な手数料:手数料の内訳や説明が不明で、人材紹介会社から、契約時に認識していた金額とは異なる金額の手数料を請求された場合。・早期退職による返金問題:採用者が早期退職した場合の返金規定が明記されていない場合。・違法行為の可能性:法律で定められた上限を超える手数料請求や不適切な契約条件。 3 トラブル事例:看護師の早期退職と金銭問題 医療機関で採用された看護師が採用後1カ月以内に退職したため、医療機関は、人材紹介会社に支払った手数料の返金を求めようとしました。しかし、人材紹介会社は、契約書に人材が早期退職した場合の返金条項を入れていませんでした。 このような場合、人材紹介会社は契約書に返金について定めた条項がないことを理由に返金対応を拒否するでしょう。早期退職時の返金規定がない以上、医療機関が返金を求めるのは困難です。医療機関は、再びコストをかけて新たな採用活動をせざるを得えません。 4 人材紹介会社との金銭トラブルを避けるためのポイント (1)認定職業紹介会社から選ぶ 厚生労働省は、法令遵守及び採用・定着・マッチングについて一定の基準を満たした職業紹介事業者について、職業紹介優良事業者と認定し、認定マークを利用する権利を与えています。職業紹介優良事業者としての認定を受けるには、手数料を公開している、早期退職時の返金制度を定めている等の厳しい審査基準を満たす必要があります。職業紹介優良事業者から人材紹介会社を選んでおけば、トラブルとなるリスクを低減することができます。 (2)契約内容を確認する 以下のポイントについて契約書に記載があるか、しっかりと確認しておきましょう。契約書の内容を事前に専門家に確認してもらうことも有効です。・返金規定や保証期間・手数料の内訳・紹介を受けた労働者が早期退職した場合の対応 (3)手数料の相場を把握する 一般的には、紹介手数料は紹介した労働者の年収の30%〜35%程度が相場と言われています。この範囲は、職種や業界、紹介する人材の専門性や希少性によって異なる場合があります。例えば、エグゼクティブ層や専門職向けの人材紹介の場合、手数料率が高くなる傾向があります。一方、一般的な職種では上記範囲内に収まることが多いので、この範囲を超過する場合は慎重に判断する必要があります。 5 法律で定められた人材紹介手数料 (1)紹介手数料の上限 紹介手数料の徴収方法は、「①上限制手数料」または「②届出制手数料」の2つがあります。人材紹介会社は、事業の許可申請時に①か②のどちらかを厚生労働省に届け出ることになります。 「①上限制手数料」では、紹介した労働者に支払った6ヶ月分の賃金の11%(免税事業者は10.3%)を限度に紹介手数料の徴収が可能です。 「②届出制手数料」では、厚生労働大臣に届け出た範囲内で自由に手数料額を定めて徴収することができます。しかし、実務的には紹介した労働者の年収の50%を超えた手数料額を届け出ても許可が下りないため、実質的に50%が上限となっています。 (2)禁止行為 人材紹介会社は、職業安定法上、以下のような行為を禁止されています。・求職者側から手数料を徴収することは、原則禁止されています。・人材紹介会社は、自己の名義をもって、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはなりません。・人材紹介会社は、厚生労働大臣に対してあらかじめ届け出た職種以外について、人材紹介を行うことは出来ません。また、港湾運送業務及び建設業務は一律に人材紹介が禁止されています。 6 医療機関経営者が取るべき対策 (1)契約時の注意点 人材紹介会社との契約書の内容を十分に確認し、手数料額や早期退職時の返金について不明瞭な点があれば契約を締結しないことが重要です。 (2)雇用条件の見直し 採用した労働者が長期雇用となるかは、採用した側の企業努力も必要です。労働者が長期間勤務しやすい環境を整えるため、以下のような取り組みを行うことが考えられます。・柔軟な勤務体制の整備・福利厚生の充実・メンタルヘルスサポートの提供 (3)相談窓口の活用 人材紹介に関するトラブルについて、厚生労働省や各都道府県の労働局が相談窓口を設置しています。トラブルが発生した際は、各相談窓口を積極的に利用してアドバイスを得るようにしましょう。 7 弁護士への相談の必要性 人材紹介会社との契約内容に問題がある、人材紹介会社が返金対応を拒否するといったトラブルが発生している場合、契約書の内容を精査して法的な観点から問題解決を検討する必要があります。早期に適切な対応を講じることで、トラブルが大きくなることを未然に防ぐことも出来ますので、人材紹介会社とのトラブル発生時には、弁護士にご相談ください。 8 まとめ 医療機関が人材紹介サービスを利用する際には、信頼できる業者の選定や契約内容の確認が重要です。円滑な人材採用が実現すれば、医療機関の経営を安定につながります。トラブルが発生した際には、法律に基づいた適切な対応を講じることで、金銭トラブルのリスクを最小限に抑えることができますので、早期に相談窓口や弁護士を活用して適切な解決策を講じることが必要です。
CONTACTお問い合わせ
病院・クリニック・医療機関を
法的リスクから守る
弁護士法人
法律事務所瀬合パートナーズ
兵庫県弁護士会所属
受付時間/ 平⽇9:00–20:00 ⼟⽇応相談

ACCESSアクセス
-
神戸事務所
KOBE OFFICE〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階FAX:078-382-3530
-
姫路事務所
HIMEJI OFFICE〒670-0913
兵庫県姫路市西駅前町73姫路ターミナルスクエア6階FAX:079-226-8516