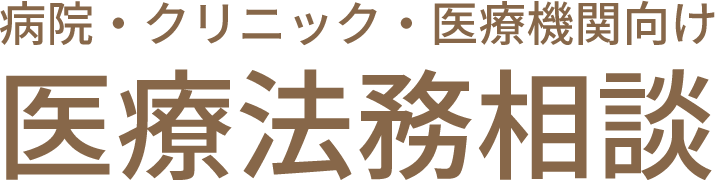医療法務コラム
医療法人の経営権争いが起きたときの対応について弁護士が解説
1.医療法人における「経営権争い」とは?
医療法人には、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。社員総会は、株式会社の株主総会に相当しますが、株主総会とは異なり社員が一人一個の議決権を持ち、同権利を行使します。そのため、株式会社のようにより多くの出資を行ったから、多くの議決権を有するということにはなりません。より多くの社員の賛同を得ることができれば、多数派になるという形になります。
そして、「経営権争い」とは、法人の意思決定権や運営の実権を巡って、理事や出資者、あるいは親族間で対立が起こることを指します。上記のような、医療法人の仕組みの下では、より多くの社員の賛同を得られれば、多数派となり、法人の意思決定権や運営の実権を握ることにつながります。したがって、争いが顕在化すると、これまで医療法人での貢献度が高かった人物ですら、多数派により法人から追い出されることもあり得ます。
2.経営権争いが表面化したときの典型トラブル
経営争いが表面化した場合、以下のようなトラブルが発生することが典型的には見られます。
⑴ 理事会の開催や決議をめぐる紛争
理事の任免や報酬、重要な契約の締結などを巡って理事会の決議がまとまらず、法人運営が停滞す る事態です。無効な決議や、逆に決議ができない状況が続くと、法人の法的な正当性が問われる可能性もあります。
⑵ 理事長の解任・交代に関する争い
理事長の解任や交代を巡って、現職理事長と他の理事や出資者が対立するケースがあります。理事長の権限が大きいため、このポジションを巡る争いは特に深刻化しやすいです。
3.弁護士が関与するメリット
⑴ 法的立場の整理と主張の明確化
関係者間で法的な権利義務が不明確なまま対立が続くと、感情的な争いになりやすいです。弁護士が介入することで、法や、定款、規則といった正当な根拠に基づき、法的に有効な主張を構築することが可能になります。
⑵ 訴訟対応による
最終的に訴訟に発展した場合でも、弁護士が最初から関与していれば、訴訟対応がスムーズに進みます。法人の混乱を最小限に抑えることが期待できます。
4.トラブルを未然に防ぐためにできること
⑴ 定款・規則の見直し
医療法人の定款や規則が曖昧な場合、解釈を巡って争いが生じやすくなります。専門家の助言を得ながら、意思決定のルール、理事長の選出方法、任期、解任手続きなどを明文化しておくことが重要です。
⑵ 定期的に弁護士などの専門家によるチェックを受けることで、法人内部のリスクを早期に発見し、適切に対処することができます。特に親族経営の場合、身内の間で問題が見過ごされやすいため、外部の視点は非常に重要です。
5 まとめ
医療法人内部において、経営争いが生じますと、法人の存続が危ぶまれるほどの重大な事態に陥りかねません。
そこで、トラブルが生じる前、あるいはトラブルが生じた後にでも、弁護士に相談し混乱を最小限に抑えることが極めて重要となって参ります。